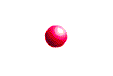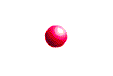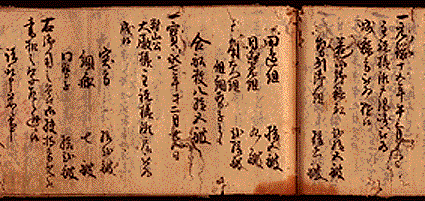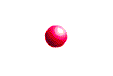
吉宗と角右衛門
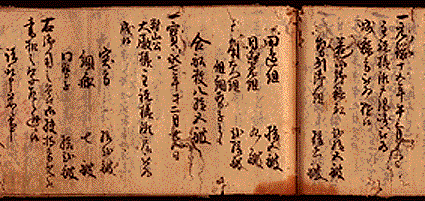
一、元禄十五年午三月■日主税様瀬戸湯崎へ■為成鯨方遊為成候
若山御鯨船 弐拾五艘
勢州御組 拾六艘
田辺組 拾五艘
周参見組 九艘
角右衛門組 弐拾艘
但網勢子とも
合船数 八拾五艘
一、宝永七年寅二月三十日
對山公大殿様主税様瀬戸江成リナサレ
突方 拾弐艘
網船 七艘
同勢子 拾弐艘
右御用之節御扶持方受取書控之写左之通ニ候
ここに記されている「主税様」とは主税守頼方、つまり徳川吉宗が5代紀州藩主になる以前の名で、初代紀州藩主・頼宣(徳川家康の第十子)の捕鯨を重視した政策が、寛文7年(1667年)に家督を継いだ2代藩主・光貞に、更にその第四子・頼方即ち吉宗へと引き継がれました。光貞の嫡子・3代藩主、綱政が元禄11年(1698年)に家督を継ぎましたが宝永2年(1705年)5月に他界、同年8月には父・光貞が、更に第三子の4代藩主・頼職も9月に他界しております。そして、第四子の頼方が5代藩主となります。従って上記の文書は吉宗によった捕鯨だと思われます。
元禄15年(1702年)と宝永7年(1710年)に瀬戸・湯崎(和歌山県白浜町)で捕鯨を観覧したとしていますが、勢子船(15人乗り)と網船(12人乗り)の人員総計と陸で指揮する者や参観者の推計を考えると、陸・海共に壮大な人員が推測され、これは捕鯨というより水軍の軍事訓練だと思われます。吉宗の祖父・頼宣が行った軍備を兼ねた大規模な捕鯨を再現させたのではないでしょうか。
吉宗は鯨方を重視していたらしく、浦方制度を取り入れて、紀州藩内で有事(異国船の侵入など)の際には狼煙(ろうえん)を焚いて熊野から和歌山までの連携の煙信号で知らせるようにさせました。鯨山見はその役割をも果たしたので、太地鯨方は紀州藩との結び付きが強かったようです。そのため、角右衛門は紀州藩勘定奉行代々直支配地士、武士の礼服である熨斗目(のしめ)着用御免という身分を与えられておりました。(地士とは、藩士ではありませんが、その地域の豪族で、戦時体制となった時には地域の指揮監督権を持ち、名字帯刀を許されておりました。)また、新宮領主・水野公からも格別の扱いがされております。貞享5年(1688年)2月に以下の指示がなされています。
御領分大庄屋共ヘ御扶持方ニ而も御切米ニても被下候哉と御尋ニ付、太地角右衛門壱人ニハ扶持方取セ申候、其外ハ扶持方ニ而も切米ニ而も取セ不申候由御申達候
(慶長ヨリ元禄年中旧記書抜覚帳)
吉宗は、享保元年(1716年)に8代将軍となってからも、江戸で鯨船を建造して非常災害用に役立てています。

10/22/1977