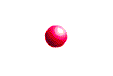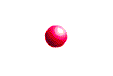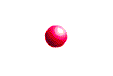
太地姓について
2/8/1998
太地家は、元々「和田」姓を名乗っていましたが、初代角右衛門頼治の時、紀州藩主・徳川光貞より太地浦の支配者として「太地」姓を賜りました。
太地浦では既に「泰地」姓がありましたが、この家は先祖を異としております。しかし、捕鯨事業開始後、「太地一類」として、和田系8家、泰地系2家の計10家が親類として明治時代まで世襲され、その頂点に太地家がありました。
我が家の文書には「角右エ門組太地鯨方ノ号、世ニ聞ヘヲ取ル君公ヨリ姓ヲ太地ト賜フ」とありますが、では何時太地姓を賜ったのでしょうか。当時の文書によっておおよそ確認することができますが、正確な年代がまだ特定できていません。
初代角右衛門頼治は、延宝5年(1677年)に兄、金右衛門頼興に代わって家督を継ぎますが、太田・太泰寺(那智勝浦町)文書に「寛文六年(1666年)丙午八月上旬十八ケ村庄屋連名 太田庄大庄屋和田角右衛門」とあって、この時既に実質的な家督を継いでいたであろうことが窺えます。
また、太地・順心寺には2代目角右衛門頼盛(当時は与市郎)の娘が早世した時、六地蔵が建てられていますが、それには「貞享元甲子(1684年)三月二八日和田与市郎」とあり、この時にはまだ「和田」姓ですが、貞享5年(1688年)2月の慶長ヨリ元禄年中旧記書抜覚帳には「・・・太地角右衛門壱人ニハ扶持方取セ申候・・・」、また太田・太泰寺本堂創建棟札には「元禄二年(1689年)創建・・・大庄屋太地角右衛門」とあって、この1684年から1688年までの4年の間に改姓されたものと思われます。ただ、初代角右衛門頼治の元禄12年(1699年)没の墓石には「和田惣右衛門頼治」とありますが、元禄5年(1692年)の「桶屋入会口上一札控」では「太地惣右衛門」とあるので、おそらく頼治の生前、和田姓の時に自身の墓石を建立したのでしょう。とすれば、墓石を建立した時点では既に「惣右衛門」と改名して隠居となっていたことがわかります。元禄3年(1690年)10月に太地・飛鳥神社を再興し、現在の祭典の原形を作った2代目角右衛門頼盛はこの時「與市郎」を名乗っているので、元禄3年(1690年)から元禄5年(1692年)の間に初代角右衛門が隠居となったものと思われます。従って、「和田」から「太地」に改姓されたのは1680年代後半、初代角右衛門頼治が隠居したのは1690年代前半だと思われます。